現在位置 ホーム > 市政情報 > 市長・議会・各種委員会 > 市議会 > 市議会の活動・取り組み報告(議会だより・SNS・委員会の活動・議会改革など) > 市議会だより「ひびき」 > 市議会だより「ひびき」(令和7年発行分) > 取手市議会だより「ひびき」第257号(令和7年11月1日発行) > 一般質問(定例会3日目)(ひびき257号)
ここから本文です。
一般質問(定例会3日目)(ひびき257号)
ウェブ版ひびき257号リンク
議員は市長などに対して、市の事務の状況や将来の方針などを質問することができます。この質問を「一般質問」といいます。
今定例会は17人の議員が一般質問を行いました。
9月2日(定例会初日)と9月3日(定例会2日目)、9月9日(定例会4日目)の一般質問の内容は、次のリンクからご確認ください。
一般質問(定例会初日・2日目)(ひびき257号)ページへのリンク
議会だより作成支援サービスによる要約結果を掲載します
株式会社アドバンスト・メディア社の議会だより作成支援サービス及び議会事務局職員により要約したものを掲載します。
議会だより作成支援サービスにより、会議録の中から、議員が行った質問とそれに対する答弁を要約して、抽出することができます。
9月4日(定例会3日目)
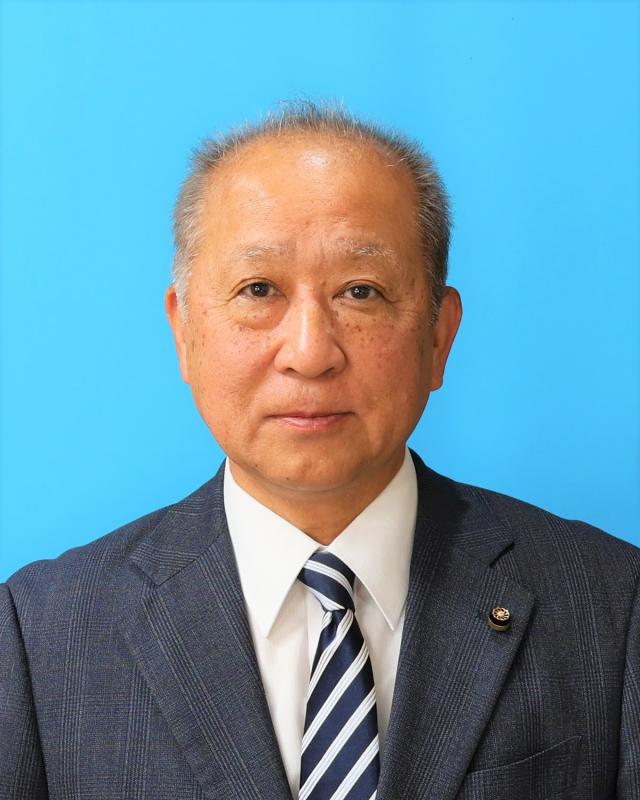 小堤 修議員
小堤 修議員
環境対策の推進について
- 異常気象による取手市民への影響と予防対策
- 身の回りの環境変化に対する一人一人の気付きアップ
- 自然環境と生活環境が心地よく一体化するための方策
- 私たちを取り巻く様々な環境変化を踏まえた目指すまちの未来像
AI要約結果
- 小堤議員 熱中症リスクへの対策として、小中学校の空調設備整備の進捗状況を伺う。
- 教育部長 現在、小中学校20校の体育館及び武道場への空調設備整備を進めている。本年度は小学校を先行して実施し、11月末に完成予定、中学校は部活動のスケジュールを考慮して、11月以降に施工を開始、来年2月末に完成する予定である。これにより、熱中症対策をはじめとした児童生徒等の安全で快適な学習環境が図られるとともに、災害時における避難所環境の改善や防災機能の強化にもつながると考えている。
- 小堤議員 不法投棄の実態と対策について、地域連携による「捨てさせない」環境づくりが必要ではないか。
- まちづくり振興部次長 不法投棄は環境汚染や景観悪化などの問題を引き起こし、社会全体に悪影響を与える。市では、職員によるパトロールや広報による啓発のほか、不法投棄ボランティア監視員制度や地域郵便局との協定、また県はごみ拾い活動のSNS「PIRIKA(ピリカ)」の機能を使った不法投棄に関する情報提供をお願いしている。地域住民との連携が重要であり、これらの対策をさらに充実させ、地域環境の保全と公衆衛生の向上に努めていきたい。
- 小堤議員 歴史的意義がある下高井の高井城址公園をきれいに整備することで、人が集まる憩いの場になると思うが、今後の整備や管理について伺う。
- 建設部次長 高井城址公園は四季折々の自然や地域の歴史に触れられる特色ある公園。豊かな自然環境を次世代に引き継ぎ、都市と自然が調和した住環境を保持していくとともに、市の魅力発信にも活用していきたい。
- 小堤議員 脱炭素と循環型社会を目指すまちの未来像について、SDGs(エスディージーズ)の目標を踏まえた市の取り組みを伺う。
- 政策推進部長 温暖化は世界的な課題であるが、現実的には人の生活、経済活動のためのエネルギー使用に伴うCO2排出を完全に止めることは難しい上、エアコン整備など迫り来る暑さへの対応を優先せざるを得ない。だからこそ一人一人の意識を高めることや次世代を担う子どもたちへの環境教育が重要と捉え、総合計画に位置づけて市民の皆様と共に取り組んでいきたい。
 根岸裕美子議員
根岸裕美子議員
産後ケアの在り方と利用しやすい制度設計について
- 産後ケアの目的の確認
- 本当に必要な人が使える制度になっているか
- 医療機関との連携・調整
- 利用方法の改善提案
AI要約結果
- 根岸議員 産後ケア事業の申請手続きを24時間いつでも可能とするため、子育てアプリ「ToriCo(トリコ)」から申請できるようにしては。
- 保健センター長 「ToriCo(トリコ)」を活用した申請は、利用者にとって利便性が高い選択肢となる。今後、前向きに検討していきたい。
- 根岸議員 産後ケアにおいて、家事サポートを行う家事支援団体や、産前産後の母親に寄り添いサポートする専門家である産後ドゥーラとの連携を進めるべきではないか。
- 保健センター長 産後ケア利用者が、産後ドゥーラや家事支援サービスを併用することは有意義と考えるが、これらの団体は民間事業者であり、公費で連携する場合には幅広い議論が必要。今後、利用者に有益な連携内容などを調査研究していきたい。
地域公共交通計画策定について
- 取手市公共交通に関するアンケート調査の結果
- 様々な調査結果から見えた課題は
- 学生に対する支援策
- 市民への情報提供、啓発
- 計画の方向性、骨子
AI要約結果
- 根岸議員 学生に対する通学補助制度について、高齢者向けコミュニティバスのシルバー割引のような支援策を導入しては。
- 都市計画課長 駅から離れた高校に通う生徒がスクールバスや路線バスを利用していることは把握しており、交通事業者にとっては安定した収益と路線維持の助けとなっている。通学に交通費がかかるという点は、中学・高校・大学のどの年代にも当てはまるため、特定の年齢層に対する支援は公平性の観点から慎重に検討する必要がある。通学定期の購入が経済的負担という意見については、今後の運行サービスの見直しの参考になるよう交通事業者に伝えていきたい。
- 根岸議員 地域公共交通計画が策定された後も、地域住民との意見交換の場を持ち続けることが有益。市民への情報提供や啓発は、どのようなアプローチを考えているか。
- 都市計画課長 公共交通の利用促進には、市民と共通認識を持つことが重要。自動車への高い依存から公共交通や徒歩など多様な交通手段への転換を目指し、モビリティ・マネジメントを進めていく。具体的には、小中学校でのバス乗車体験会や、企業に対して通勤時の公共交通利用の促進など、公共交通を生活の中に取り入れる意識の醸成を図っていきたい。
(解説)モビリティ・マネジメント 環境や健康などに配慮した交通行動を、大規模、かつ、個別的に呼びかけていくコミュニケーション施策
広域避難受け入れ体制と取手市原子力災害防災計画策定について
- 広域避難受け入れ想定
- 広域避難受け入れに関する市民への情報提供
- 取手市原子力災害防災計画が必要では
AI要約結果
- 根岸議員 取手市は福島第一原子力発電所事故でホットスポットとなった経験があるが、原子力災害防災計画が必要ではないか。
- 総務部次長 取手市は原子力発電所から30キロ圏外であるため、現状では原子力災害に対する防災計画は策定していない。しかし、福島第一原発事故の影響を受けた経験や国の指針を踏まえ、市民の安全を最優先に、原子力災害に対する防災計画の策定を検討する必要性を認識している。
根岸裕美子議員一般質問の動画(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
 本田和成議員
本田和成議員
救急時の選定療養費の徴収について
- 本市での徴収例と徴収数
- 教育現場や福祉施設の現状
- 市独自の具体的なガイドライン作成と徴収時の補助
AI要約結果
- 本田議員 小中学校から教育委員会に対して、救急搬送に関する意見や要望は上がっているか。
- 教育次長 学校現場では、児童生徒の救急搬送が必要な場合、ためらわず救急要請を行っているが、症状によっては判断が難しいため、救急電話相談を利用することもある。しかし、相談中に症状が悪化するリスクもあるため、学校からは選定療養費の徴収対象から除外してほしいという要望が上がっている。市としてこれを重く受け止め、県との会議の場で引き続き要望していきたい。
- 本田議員 学校や福祉施設で救急搬送時に選定療養費が徴収された場合、市独自の補助を行うことは可能か。
- 教育次長 現時点で補助を実施する予定はないが、県や他市町村の動向を注視しながら情報収集に努めていきたい。
道路・樹木の管理について
- 街路樹・学校の樹木
- U字溝
AI要約結果
- 本田議員 街路樹の寿命や近年の異常な暑さを踏まえ、植え替えや街路樹の意義・目的に沿った計画を立てる必要があると考えるが、いかがか。
- 建設部長 老木化・大木化が進み倒木の危険性が高まった街路樹については、伐採して安全性を確保している。引き続き実態調査を進め、必要に応じて間引きや若い苗木への植え替えを行い、街路樹の世代交代を図る必要がある。今後、地域の特性や街路樹が整備された年代などを考慮しながら検討していきたい。
- 本田議員 市内にはふたのない側溝が多く存在し、安全のためにふたをかけてほしいという市民からの要望にどう対応するのか。
- 管理課長 ふたをかけない理由として、清掃等の維持管理の効率性や雨水の排水・集水能力の向上があるが、市民からは歩行者の安全性を優先して、ふたをかけてほしいという要望が上がっている。ふたをかけられない構造のU字溝が多いため全ての要望に応じることは難しいが、課題として捉えている。
- 建設部長 これまで、通学路の安全確保や高齢化が進む地域など、危険性が高い場所については可能な範囲で側溝のふたかけを行ってきた。今後も、車や歩行者の安全確保、高齢化に伴う課題、維持管理の合理性、道路の交通量や幅員などを総合的に勘案しながら検討を進めていきたい。
学校給食について
- 学校給食の意義
- 本市の学校給食の現状
(1)衛生管理(異物混入)
(2)食材費高騰 - 国は小学校の学校給食無償化の方針を出したが本市の動向は
AI要約結果
- 本田議員 国は令和8年のなるべく早い時期に、小学校から学校給食費無償化を実施する方針を出した。市は今までどおり、国や県の動向を見てから対応するのか。また、無償化を実施する場合、給食の質と量を維持することは可能か。
- 教育部長 これまで、食材費が高騰しても給食の質と量を落とすさずに、国の交付金を活用し保護者の負担軽減を図ってきた。国の給食費無償化の方針は令和8年度予算編成過程で具体化される予定だが、現時点では詳細は未定。引き続き、国や県の動向を注視し、国の実施時期に合わせた対応を進めていきたい。
本田和成議員一般質問の動画(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
 鈴木三男議員
鈴木三男議員
市の財政について
-
歳出
(1)目的別歳出
(2)民生費 -
経常収支比率
-
財政力指数
-
実質収支、単年度収支、実質単年度収支
-
財政調整基金
AI要約結果
- 鈴木議員 目的別歳出状況において、農林水産業費・商工費が低い傾向にあるが、なぜか。稲作への若い担い手の参入や地場産業の活性化を図る政策に力を入れては。
- 財政部長 農林水産業費・商工費が低い理由は、市が首都圏近郊のベッドタウンとして発展してきたことに起因している。第一次産業従事者の割合が全国平均より低く、農業や商工業が主要産業ではないためである。ただし、農業公社事業円滑化補助金や創業支援・空き店舗活用事業、観光協会への補助金など、市民ニーズに応える事業はしっかりと予算化している。
- 鈴木議員 取手産コシヒカリや地元特産品など、ふるさと納税の返礼品拡充に努めてほしい。
- 財政課長 ふるさと納税の推進において、市内事業者と連携し、特産品や農産物を返礼品として提供している。具体的には漬物やお煎餅、お米、バナナポーク、サツマイモ、干し芋などが人気を博している。
- 鈴木議員 実質単年度収支が5年間黒字になっている。地方自治体が毎年度、黒字を出し続けることは、市民サービスの向上という観点から望ましいのか。
- 財政課長 実質単年度収支の黒字が継続する状況は、住民サービスへの還元が不十分である可能性を示す場合があるが、近年の黒字は交付税の再算定が主な要因。過去10年の平均では約6,800万円の黒字に過ぎず、住民サービスへの還元が不十分とは言えないと考える。
- 鈴木議員 次年度以降の予算編成では、積極財政にかじを切り、市民への公共サービス向上に充てるべきではないか。
- 財政部長 財政調整基金残高は増加傾向にあり、危機的状況から脱しているが、扶助費や特別会計への繰出金の増加、公共施設・インフラの改修費用などで財政は硬直化している。また、過去の景気悪化時には基金を取り崩して対応した経験があるため、一定規模の基金確保は必要。一方で、増加した税収を市民サービスや地域経済の活性化に還元することも重要であり、バランスを取った財政運営を目指し取り組んでいきたい。
鈴木三男議員一般質問の動画(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
 落合信太郎議員
落合信太郎議員
アフォーダブル住宅について
- 市の考え
- 東京圏との賃金格差緩和のための導入
AI要約結果
- 落合議員 中低所得者や子育て世帯が住みやすい環境の形成と東京圏との賃金格差緩和の観点から、アフォーダブル住宅導入についての市の考えを伺う。
- 都市計画課長 近年の住宅支援策として、国が住宅取得やリフォームに対する補助制度を開始しており、若い世代にとって魅力的な内容となっている。市では、国の補助金との差別化を図るため、市の定住化促進住宅補助制度である「とりで住ま入る(スマイル)支援プラン」における加算額の要件増設や緩和を検討するとともに、通勤しやすい常磐線始発駅や地価の安さを活用し、シティプロモーションを通じて若い世代や子育て世代の呼び込みを進めていきたい。
(解説)アフォーダブル住宅 中低所得者が無理なく住み続けられるよう、市場価格よりも低い家賃や価格で利用できる住宅。
学校の熱中症対策について
- 現状
- 冷蔵庫の導入
AI要約結果
- 落合議員 学校の家庭科室にある冷蔵庫を活用して、ネッククーラーなどを冷却し、児童生徒の下校時の熱中症対策に役立てることはできないか。
- 学務課長 家庭科室の冷蔵庫は家庭用であり、全員分のネッククーラーなどを保管することは不可能。また、食品を保管する目的であるため、汗ばんだものを入れることには抵抗感があり、熱中症対策に活用する予定はない。
取手駅西口交通広場の利便性向上について
- 一般車乗降場の拡大
AI要約結果
- 落合議員 取手駅西口交通広場の一般乗降スペースは限られている。利便性向上のため、無料駐車場のさらなる周知や運用改善を図るべきではないか。
- 都市整備部次長 現在、お迎えの時間に合わせて一般車乗降場を利用するよう案内しているが、いまだに待機車両が見受けられるため、ウェルネスプラザ第2駐車場を待機場として案内する運用を進めていく。今後も一般車乗降場の運用方法を駅の利用者以外にも幅広く周知し、認知度を高める取り組みを行っていきたい。
ソーラー式防犯灯の導入について
- 導入の検討
AI要約結果
- 落合議員 災害時にも点灯でき、環境にも配慮したソーラー式防犯灯の導入を検討してはどうか。
- 管理課長 ソーラー式防犯灯は高価だが、災害時の道路照明の確保や市民の安全な避難にも効果がある。他市町村の事例を参考に、運用課題や電力供給との併用の可能性を含めて調査研究を進めていきたい。