現在位置 ホーム > 市政情報 > 市長・議会・各種委員会 > 市議会 > 市議会の活動・取り組み報告(議会だより・SNS・委員会の活動・議会改革など) > 市議会だより「ひびき」 > 市議会だより「ひびき」(令和7年発行分) > 取手市議会だより「ひびき」第256号(令和7年7月15日発行) > 一般質問(定例会初日・2日目)(ひびき256号)
ここから本文です。
一般質問(定例会初日・2日目)(ひびき256号)
ウェブ版ひびき256号リンク
議員は市長などに対して、市の事務の状況や将来のかた針などを質問することができます。この質問を「一般質問」といいます。
今定例会は20人の議員が一般質問を行いました。
6月9日(定例会2日目):岡口・古谷・鈴木・久保田・小堤・山野井議員
6月10日(定例会3日目)と6月11日(定例会4日目)の一般質問の内容は、次のリンクからご確認ください。
議会だより作成支援サービスによる要約結果を掲載します
株式会社アドバンスト・メディア社の議会だより作成支援サービス及び議会事務局職員により要約したものを掲載します。
議会だより作成支援サービスにより、会議録の中から、議員が行った質問とそれに対する答弁を要約し、抽出することができます。
6月6日(定例会初日)
 入江洋一議員
入江洋一議員
ごみ分別の周知(ごみカレンダー)について
- ごみ分別の周知方法
- ごみ分別におけるごみカレンダーの役割
- ごみカレンダー配達における管理体制等
- 今後の改善策
AI要約結果
- 入江議員 不燃ごみの分別方法変更後の具体的な状況について伺う。
- まちづくり振興部次長 分別方法変更後の状況について、4月と5月のプラスチック類と金属類の収集日にそれぞれ116件と56件の問い合わせがあった。主な内容は収集日の確認や分別されていない不燃ごみの回収についてである。周知期間が短かったため、当面は通常の不燃物が金属類等の回収日に出されていても回収する方針である。
- 入江議員 ごみカレンダーの未配達を防止するための改善策について伺う。
- まちづくり振興部長 ごみカレンダーの未配達防止策として、配布時期を3月から2月に前倒しし、不測の事態に対応できる時間を確保する。また、配布方法や業者選定について近隣自治体の事例を調査し、民間業者の意見を取り入れるなどの手法を検討している。さらに、市民への分別徹底の周知を継続する。
 染谷和博議員
染谷和博議員
医療用ウィッグ(かつら)の補助について
- がん治療を受けているかたのウィッグ(かつら)の購入やレンタル費用の補助
AI要約結果
- 染谷議員 医療用ウィッグの購入やレンタル費用に対する補助制度の導入を検討してはどうか。
- 健康福祉部長 がん治療による脱毛の精神的負担は重要な課題であると認識している。医療用ウィッグの費用が患者の経済的負担となっている点も理解している。現在、取手市では補助制度は設けていないが、茨城県の補助制度が利用可能であることを承知している。今後、他自治体の事例や相談者のニーズを精査し、補助の必要性や効果を検討していく考えである。
給食センターの活用について
- 学校に通えない子どもたちに給食で社会とのつながりを届ける
AI要約結果
- 染谷議員 東京都八王子市では給食センターを開放し、学校に行けない子どもたちのために無料で給食を提供しており、給食を通じて人とのつながりを感じてもらうことを目指している。取手市も同様に、給食センターを第二の居場所として活用する取り組みは可能か。
- 教育部長 八王子市の取り組みは把握している。実際に不登校の方が家から一歩踏み出すきっかけになった事例もあり、大変素晴らしい取り組みだと感じている。
- 教育次長 取手市でこの取り組みを行う場合、給食センターが宮和田地区にあることから来所が難しく、施設自体も来所者を受け入れる想定ではないということが課題になる。また、来所者の予測が難しく、材料費の調達が困難である点や、給食センターの職員数が少ない上、不登校支援に対応できる職員の配置が難しい点も挙げられる。八王子市の柔軟な発想が大いに参考になるため、不登校支援や居場所づくりの観点からも手法を検討したい。
子ども図書館について
-
取手駅西口A街区に予定されている図書館への子ども図書館の設置
-
まちじゅう図書館
AI要約結果
- 染谷議員 太田市の「まちじゅう図書館」のような事業を取手市でも導入できるか。
- 教育部長 「おおたまちじゅう図書館」は、駅前の活性化やにぎわいを目的に、市内の商店や事務所など37館の各館長が思い入れのある本を置き、本を通じて地域とのつながりやまち歩きを楽しむ仕組みを作っている。当市でも図書館を核とした地域連携の在り方や市民と本との多様な関わり方を模索し、本を通じたまちの魅力づくりを進めたい。
高校1年生の自転車の「謎」について
- 高校1年生に自転車事故が多発しているのは小中学校での自転車教育に問題があるのではないか
AI要約結果
- 染谷議員 小学校1年生と高校1年生は、通学環境の変化などから自転車事故が急増することが知られている。しかし、実際には高校1年生が小学校1年生の4倍ほど事故件数が多く、警察庁などでも問題視されている。全国的に小中学生の自転車禁止という風潮が高まっていると考えるが、学校が教育のための機関であるという意識が欠けているのではないか。取手市において、小中学校でどのような自転車教育が行われているか。また、高校生になった際の事故防止にどの程度効果があると考えているか。
- 指導課長 小中学校では道路交通法改定を踏まえ、関係機関と連携して自転車利用時の安全意識や知識・技能について講習を実施しており、学校によっては実体験を含む取り組みも行っている。また、保護者には交通事故の現状や自転車保険の加入について周知している。しかし、高校生になってからの事故防止効果については現時点で把握していない。小中学生には飛び出しへの指導が最も大切と考えている。今後も交通安全教育を継続し、児童生徒や保護者への啓発を進めていく。
 長塚美雪議員
長塚美雪議員
地域経済の活性化について
- 地域内消費促進の取り組み
- 地域内経済循環と地域活性を促す地域通貨の導入
AI要約結果
- 長塚議員 デジタル地域通貨の導入について、地域内経済循環や地域活性化への寄与を考慮し、調査を進めるべきではないか。
- まちづくり振興部次長 地域通貨は地域経済の活性化を図る有効な手段の一つと考える。デジタル地域通貨は便利さやさまざまなサービスとの連携の広がりが期待できる。市のデジタル化が進む中で、商品券や地域通貨の導入についても、システム連携を視野に入れた提案を受けながら検討していきたい。
市民ニーズに沿った公園整備について
- 「取手市こども計画」「第三期取手市子ども・子育て支援事業計画」策定におけるアンケート結果をどう捉えているか
- 今後の整備方針
- にぎわいを創出する公園に向けて
AI要約結果
- 長塚議員 地域住民や藝大とコラボしたアートを公園に施すことで、住民同士のつながりや自分たちで造った公園としての愛着を生むことや、キッチンカーの誘致によるにぎわい創出についてどう考えるか。
- 建設部次長 市内の公園は、地域住民との連携を通じて地域全体を活性化させる可能性を秘めている。公園でのアートイベントは、特別な体験を通して子どもの創造性を育み、地域のにぎわいを創出する効果が期待できる。また、キッチンカーの出店は公園の魅力を高め、交流を活性化することが期待される。既存の公園管理にとらわれず、地域住民の声を生かしてにぎわい創出に努めたい。
6月9日(定例会2日目)
 岡口すみえ議員
岡口すみえ議員
部活動地域移行について
- 部活動地域移行
(1)文化部 - 指導者の確保状況
- 部活動に係る費用負担
AI要約結果
- 岡口議員 吹奏楽部の活動を地域に移行するに当たり、指導者の確保について、取手市の現在の取り組みと今後の課題認識および対応策を伺う。
- スポーツ振興課長 部活動の地域移行では、学校教員の指導ノウハウを活用しつつ、小学校教員や地域の吹奏楽団代表者が指導に加わっている。今後は地域連携を強化し、指導者の確保と地域クラブの充実を進める予定。
防犯、交通安全について
- 防犯対策の強化
(1)現在の防犯対策の実施状況と課題
(2)防犯カメラ
(3)地域住民との協働による防犯意識の取り組み - 自転車における交通安全対策
(1)自転車用ヘルメットの着用の現状
(2)ヘルメット着用促進のための市の施策
(3)今後の課題
AI要約結果
- 岡口議員 地域住民と行政が協働して防犯意識を高めるための具体的な取り組みについて伺う。
- 総務部次長 地域住民との協働として、防犯連絡員と連携し、防犯キャンペーンや注意喚起活動を実施している。また、地域の実態に即したパトロールや児童の見守り活動を通じて、市民の防犯意識の醸成に努めている。
- 岡口議員 自転車用ヘルメット購入補助金を本市でも導入し、着用率向上を図るべきではないか。市の今後の課題を踏まえ、答弁を求める。
- 総務部長 ヘルメット着用率向上のため、まずは周知や啓発活動を優先的に実施する考えである。高校生からは「ヘアースタイルが乱れる」「かぶるのが面倒」といった声が多く、高齢者に対しても補助金交付の効果がすぐに見られる状況ではない。現状では、ヘルメット着用の重要性を認識してもらうことが必要だと考えている。
高齢化への対応について
- 高齢化社会の現状
(1)市の対応、支援策
(2)今後の課題 - 認知症予防
(1)認知症予防策についての現状
(2)今後の課題
AI要約結果
- 岡口議員 認知症予防のための生活記録ノートについてどのように考えているか。
- 高齢福祉課長 認知症ガイドブックと、終活用の未来ノートを配布している。高齢者にとって「書く」行為は脳の活性化や生活リズムづくりに効果的だと考えている。今後は新たな配布物を増やすのではなく、既存のガイドブックや未来ノートの周知・普及を進め、利用者の声を反映して改善を図りたい。
 古谷貴子議員
古谷貴子議員
「ぼくは風船爆弾」の映画の上映推進について
- 戦後80年の取り組みとして、戦後を体験していない世代、特に中学生に映画の上映の推進を
AI要約結果
- 古谷議員 映画「ぼくは風船爆弾」を教育に活用し、戦争体験のない若い世代、特に中学生に平和の尊さを伝えることについて、市としてどのように考えているか。
- 指導課長 「ぼくは風船爆弾」は茨城県北茨城市での史実を基にして、10代の女学生を描いた映画となっており、当市の中学生にとっても大変興味深い。映像を通じて戦争の実態を学び、討論や感想の共有によって戦争の記憶を未来へつなぐことができると考えている。さまざまな方法や媒体を活用して平和教育を推進し、次世代に平和の願いをつなぐ取り組みを行っていきたい。
不燃ごみの削減及び回収について
- 不燃ごみの分別とごみを減らす取り組み
- プラスチックごみの回収日程の増加
- スーパー等での回収状況
- 不燃ごみを減らすための市民の意識向上への呼びかけ
AI要約結果
- 古谷議員 取手市において、プラスチックごみの回収を隔週から毎週に増加させる取り組みについて、どのように考えているか。
- まちづくり振興部次長 取手市ではプラ容器の回収を隔週で行っているが、家庭ごみ排出量実態調査の結果から隔週回収が現状に合っていると考えている。ただし、市民から保管場所の問題で毎週回収を希望する声があるため、常総環境センターや委託業者との調整、人員・設備の確保、財政面の検討を進める。
- 古谷議員 ごみ減量に向けて市民の意識向上を図りながら、リフューズ(過剰な包装等のごみになる物は進んで断ること)、リデュース(ごみの発生・排出を抑制すること)、リユース(不要となった物の再利用に努めること)、リサイクル(ごみとして排出された物を再び資源として使うこと)の4Rの推進をどのように発信していくのか。
- まちづくり振興部長 ごみの減量には市民の意識向上が重要であり、啓発活動を継続していく。市ホームページやSNSで情報発信を行い、出前講座や講習会を実施する。不燃ごみの減少は市民、企業、行政が協力して取り組むべきであり、企業にはリサイクル可能な素材の使用や簡素化が求められる。市としては4Rの取り組みを進め、持続可能な社会の実現を目指す。
 鈴木三男議員
鈴木三男議員
木造住宅耐震化について
- 令和5年度及び令和6年度の無料耐震診断した件数と耐震設計及び耐震改修工事に補助金を支給した件数
- 耐震診断の「上部構造評点」の結果を踏まえて、どのように判断して補助金を支給するのか
- 木造住宅耐震化事業に対しての周知方法は
- 予算化した以上に申請があった場合の対応は
- 防災ベッド、耐震シェルター設置に対して補助金を検討する考えはないか
AI要約結果
- 鈴木議員 当市は旧耐震基準で建築された木造建築が数多く、南海トラフ地震や南関東地震などの大地震の発生に伴い、多くの住宅が倒壊する恐れがある。木造住宅の耐震化によって市民の生命・財産を守ることは喫緊の課題だと考えるが、木造住宅耐震改修工事の補助はどのように周知しているか。固定資産税の納税通知書に周知チラシを同封してはどうか。
- 建築指導課長 木造住宅耐震化事業の周知方法として、市広報紙や市ホームページでの案内、市民向けおよび改修事業者向け説明会の開催、過去に耐震診断を受けたかたへのメールや訪問による案内、対象住宅への啓発用チラシのポスティングなどを行っている。また、納税通知書にチラシを同封することは、周知の手段として非常に有効だと考える。他市町村の取り組みの効果を参考にしながら、関係機関と連携し、より効果的な周知方法を検討していく。
地方債(市債)について
- 令和7年度の地方債(市債)残高について、どのように分析しているか
- 緊急防災・減災事業債
(1)起債手続
(2)どのような事業に充当したか
(3)利率、償還期限、償還方法 - 臨時財政対策債
(1)本市では、これまで臨時財政対策債を満額発行していたのか
(2)臨時財政対策債の償還は、どのような方法で交付税措置されるのか
(3)国は、臨時財政対策債を将来返してくれると言っているが、本当に返してもらっているのか
AI要約結果
- 鈴木議員 緊急防災・減災事業債は具体的にどのような事業に充当しているのか。
- 財政部長 緊急防災・減災事業債は、防災基盤整備や公共施設の耐震化などのうち、緊急性・即効性のある事業が対象になっている。当市では、小中学校の耐震補強や災害用設備整備などに活用しており、令和7年度も体育館関連事業に活用している。今後も積極的に活用していく方針である。
- 鈴木議員 本市では臨時財政対策債を過去に満額発行してきたか。
- 財政部長 取手市は平成13年度の制度開始以来、臨時財政対策債を基本的に満額発行しており、累計約376億円に達している。発行しない場合でも長期的な損得はないが、一般財源不足を基金などで補う必要があるため、財政運営の安定を図るため満額発行を続けている。
鈴木三男議員一般質問の動画(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
 久保田真澄議員
久保田真澄議員
女性の就労やキャリアアップの支援について
- 母子家庭の就労支援
- 女性の専門職資格取得等支援事業補助金の導入
AI要約結果
- 久保田議員 母子家庭の就労支援について、市としてどのような取り組みを行っているのか。
- まちづくり振興部長 本市は、母子家庭への就労支援を重要視し、ハローワーク龍ケ崎と連携して「ふるさとハローワーク」や「マザーズコーナー」を設置し、就労相談や家庭と仕事の両立支援を行っている。また、資格取得を支援する給付金の支給や、ITスキル向上の職業訓練を紹介するなど、幅広い世代の就労ニーズに応えるため、関係機関と連携して取り組みを進めている。
- 久保田議員 女性の専門資格取得等支援事業補助金の導入について、市の考えを伺う。
- まちづくり振興部次長 女性の専門資格取得支援事業補助金は、資格取得費用の一部を補助し、育児や介護でキャリアを中断した女性の再就職やスキル習得を支援する施策である。学びの場の提供によりネットワーク形成や情報交換を促進し、相互に成長していくことが期待される。市は関連計画を踏まえ、制度調査を進める方針である。
5歳児健診の実施について
- 発達障がいの早期発見・早期支援に向けて市の取り組み
- 5歳児健診の実施を
AI要約結果
- 久保田議員 5歳児は心身の発達が著しく、この時期の健診により早期の問題発見や適切な支援につながる。5歳児健診の重要性について、市の見解を伺う。
- 健康福祉部長 5歳児健康診査は、児童の成長や発達以外に、集団での振る舞いを評価することで、日常生活や人間関係、社会的な発達の状況を把握し、適切な支援につなげることができる。また、適切な生活習慣を身に着けるための健康教育・保健指導を行い、学童期・思春期の課題に対応していくことが重要となる。関係機関と連携し、子どもたちが健やかに成長できる環境を整備する必要がある。
終活支援について
- 身寄りのない高齢者への対応
(1)葬儀・納骨・遺品の整理など - 終活支援事業の導入
AI要約結果
- 久保田議員 広島県東広島市では、身寄りのない高齢者が緊急連絡先や遺言書の保管場所をあらかじめ市に登録するという終活情報登録事業を行っている。取手市としての終活支援の取り組みについて伺う。
- 高齢福祉課長 当市が現在発行している未来ノートは、思い出、やりたいこと、没後に託したいことを書き込むことができる。また、発行の準備を進めている終活便利帳は、介護・相続・葬儀・死後事務委任・任意後見など、終活に関するさまざまな疑問を解消できる内容になっており、未来ノートと併用していただくことも想定している。
久保田真澄議員一般質問の動画(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
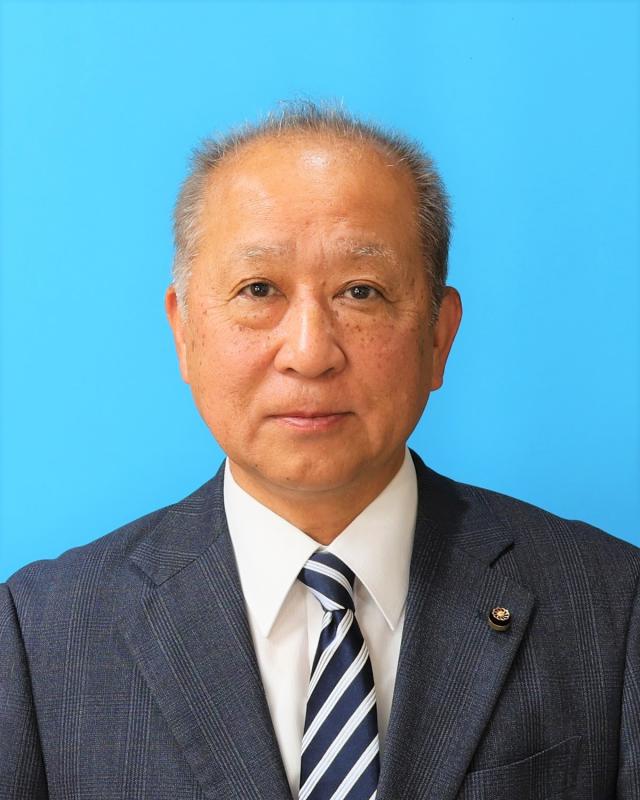 小堤 修議員
小堤 修議員
安全安心対策の推進について
- 市役所庁舎の防火管理
- 消防団の課題
- 多種多様化する犯罪への対応
- 防災教育
- 防災に特化した部署の創設
AI要約結果
- 小堤議員 白岡市役所の火災を踏まえて、市所有の施設全体において、火災を防ぐための具体的な対応策はどのように講じているのか。
- 管財課長 設市が運営する施設では、建物形状や使用目的に応じた火災予防計画を策定し、消防法に基づく防火設備を置している。また、取手庁舎および藤代庁舎では夜間警備員を配置し、その他の施設ではセンサーを使用した機械警備を導入している。これらの対策を通じて、市民が安心して利用できる環境づくりに取り組んでいる。
- 小堤議員 火災や大災害への対応は消防団の助力が必要不可欠だが、当市では消防団員の減少が大きな課題になっている。団員数減少の要因と対応について伺う。
- 消防長 消防団員減少については、若い世代の消防団離れ、サラリーマン世帯の増加、活動の負担感などさまざまな要因が考えられる。総務省消防庁では団員報酬の改善や、アンケート調査を通じた団員確保のマニュアルの作成などの対策を講じており、当市においても、出初式や消防フェスタ、新春マラソン大会などのイベントでの募集活動や歩道橋への横断幕の掲示などを行っている。
児童数の減少傾向について
- 今行うこと(考えること)
- 将来に向けて考えること
AI要約結果
- 小堤議員 児童数減少への対応策として、自由学区や学校選択制、児童数の平準化、空き教室の利活用に関して、具体的な方策や課題をどのように考えているのか。
- 学務課長 自由学区や学校選択制の長所として、保護者が学区に縛られず子どもに合った学校を選べる点が挙げられる。一方で、登下校時の安全確保や地域コミュニティーとの交流減少などの課題がある。教育委員会としては、これらの長所や課題を調査研究し、先行事例を参考にしていく。
こどもまんなか社会の実現に向けた「取手市こども計画」の実効性について
- 目指す未来の方向性
- 検討と取り組み
AI要約結果
- 小堤議員 取手市こども計画における子どもの居場所づくりについて、現在どのような検討が行われているか。
- こども部長 子どもの居場所づくりは、こども大綱や国の指針で重要とされ、安全安心な居場所の充実が自己肯定感や社会で生き抜く力を育む施策と認識している。昨年度の調査や関係者との協議を通じて課題を明らかにし、企業や地域と協力しながら子どもや若者の声を聴きつつ検討を進めていく。
小堤 修議員一般質問の動画(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
 山野井 隆議員
山野井 隆議員
市制施行55周年について
- 周年行事の意義は何か
- 予定されている事業
AI要約結果
- 山野井議員 市制施行55周年記念行事について、現時点で予定されている具体的な事業内容を教えてほしい。
- 政策推進課長 55周年記念事業として、藝大フィルハーモニア管弦楽団による演奏会、取手ロゲイニング、ドローンサッカー体験会を予定している。これらは新規事業も含まれており、事業のPRも兼ねて55周年を広く周知することを目的としている。
- 山野井議員 市制施行55周年の情報公開が不足していると感じる。ホームページやSNSでの発信が弱く、記念ロゴやキャッチフレーズもない。地域資源を活用したプロモーションを強化すべきではないか。
- 魅力とりで発信課長 市制施行55周年を迎えるにあたり、市の魅力を再確認し、市民の郷土愛を深めるための情報発信の準備を進めている。予算の範囲内で創意工夫を凝らし、秋以降に順次公開する予定である。
取手駅東口のバリアフリーについて
- 東口の利便性向上を求める声は大きい。これまでの経緯
- バリアフリーを含めた自由通路計画
AI要約結果
- 山野井議員 取手駅の東西自由通路の整備と東口のバリアフリー動線確保を一体的に捉え、JR東日本や国交省との協議を進める意向はあるか。財源がないからと諦めず、地方債を発行してでも進めるべきではないか。
- 都市整備部次長 取手駅周辺の再開発事業や複合公共施設整備を進める中で、東西自由通路の整備の必要性を認識している。また、平成21年度にJR東日本が橋上化を断念した経緯があるが、現在の状況は大きく変化しているため、再度協議を行う意向である。自由通路の整備や橋上化が実現すれば、東口からの新たなバリアフリールートも確保されることとなる。適切な時期を見計らい、JR東日本に協議を申し入れていきたい。
学校運営協議会委員について
- 活動内容を伺う
- 委員の選定方法
- 期待される効果を明確にするべきと考える
AI要約結果
- 山野井議員 学校運営協議会の人選や議事録、内容の可視化を進め、市民に成果を分かりやすく提供する仕組みを作るべきではないか。
- 生涯学習課長 当市において、令和7年度の協議会の委員に関しては、各学校長から意見を聴取し、任命に反映している。現在まで公募は行っていないが、文部科学省の例や市町村の裁量を踏まえて今後の人選について検討していく。また、地域住民の理解・協力の促進のために、協議会の結果を積極的に提供する必要があり、教育委員会としても広報活動を継続し、学校に対して、地域住民や保護者へ情報提供をするよう助言を行っていく。